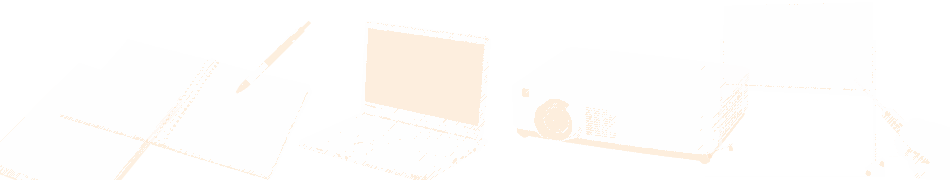eラーニングのランダム出題も「学ぶん化」
eラーニングの弱点
会社の先輩A「B、もう eラーニング終わった?」
会社の後輩B「さっき、終わらしましたよ。案外かんたんですよ」
会社の先輩A「今回、テストもあるんだろ」
会社の後輩B「入力した解答控えてますけど、要ります?」
会社の先輩A「いいね、気がきくじゃん。じゃあ、さっさと済ましちゃおう」
eラーニングの場合、従業員のスケジュールに合わせて研修を受講することが可能です。eラーニングのサーバーに接続できる環境があれば、どこでも受講ができます。受講者が集まる必要もありません。やれる人から順番にやっていけばいいのです。
ところが、テストを実施する場合、上記のように先にやった人の解答をそのまま流用してしまうという問題が発生します。せっかくテスト結果をもとに理解度を確認しようとしても、正確な習熟度を把握することは難しくなってしまいます。また、受講者の取り組み意識も希薄になります。
eラーニングの問題解決策
上記の問題を解決するための方法として次の 3つがあります。
- 1. 全員同時にeラーニングを受講する
いつでもできる eラーニングの特長が薄れますし、同時アクセス数制限の問題もあります - 2. 受講者をグループ分けし、そのグループ単位で一斉に eラーニングを受講する
厳格に対応するならこの方法もありです - 3. テスト問題をランダム(無作為)出題にする
eラーニングのシステムがランダム出題対応であれば、この方法がベター
※ランダムに出題させるため、テスト問題を多く準備する手間はかかります
ランダム出題の効果
以前、実際にランダム出題を実施したときには、以下のような反応がありました。
- 1. 想定どおり、答えを教え合う行為があった
時間的制約の厳しい部門(営業など)で多い - 2. 彼らは自分の問題と同僚の問題が違うことに気づいた
自分が見ている画面上に教えてもらった選択肢がなく、気づくというパターン - 3. 問題が違うことで、再度テキストを読み直すなど関心度が高まった
※ランダム出題する告知をせずにスタートしましたが、すぐに問い合わせがきました。
テスト終了後に、「問○の答え何にした?」などと同僚同士で答え合わせをしているのです。
出題パターンを3倍くらいに増やしたので、問題のバリエーションも多彩になり、興味をひいたようです。これも学習意欲を高める一つの方法でしょう。