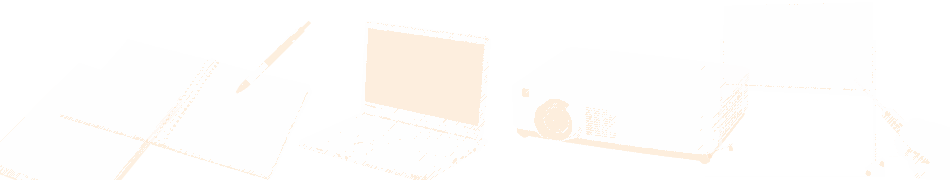社内講師の見つけ方−誰が教える?
従業員全員が講師候補
人材育成内製化をすすめる上で、ボトルネックになりそうなのが、教える「講師」をどうするかでしょう。内製化をしようとするのですから、当然講師候補は社内から見つけ出すことになります。
ここで、講師になる人のイメージを勝手にふくらませ過ぎないことが大事です。最初からプロフェッショナルのように上手くできる人ばかりではありません。基本的に全従業員が「講師候補」です。人には何か得意分野があるでしょうし、社内で一番ものしりの分野もあるでしょう。自分では大したことがないと思っていても、何かに役立つ可能性は十分にあるのです。
社内講師の見つけ方 その1(スカウト方式)
最初は自ら進んで講師に立候補する人も少ないでしょうから、人材育成内製化を推進する部門の方が中心となって、講師候補を選び出していきましょう。
有資格者をピックアップ
全従業員の所有資格を確認しましょう → 所有資格をもとに、研修可能な講座をリスト化
講師経験者をリストアップ
過去に講師経験がある人を全員リストアップ → 実績講座と研修可能講座をリスト化
”社内生き字引”をリストアップ
会社の歴史や事情について精通しているしている人をリストアップ → 講師内定
スペシャリストをピックアップ
財務、生産、法務、営業等々、各部門の専門家をリストアップ → 各分野の講師内定
社内講師の見つけ方 その2(公募方式)
スカウト方式で講師が見つかれば、次は社内公募方式で広く講師役を募集しましょう。ここでは、立候補だけでなく、他薦をどしどし募りましょう。「講師の大役」というイメージを和らげるために、研修タイトルを例示して、心理的負担を軽減させましょう。
【研修タイトル例】
- 『エクセル超初級入門―電卓、集計用紙卒業編』
- 『これだけ必殺技』
- 『再再再入門―ワードの入口だけ』
- 『社長の履歴書』
- 『加減乗除だけでわかる会社の数字』
- 『スペシャリスト○○さんに聞く 質問会』
- 『会社の歴史―その時わが社は動いた』
- 『商品開発裏話』
- 『自分の税金・社会保険料 徴収のカラクリ』
- 『切り貼りで始めるパワーポイント入門』
- 『仕事が見えてくるシリーズ 店長の一日』
- 『仕事が見えてくるシリーズ バイヤーの一日』
- 『仕事が見えてくるシリーズ 営業の一日』
- 『簿記入門前 10級レベル編』
*研修タイトルは「これなら自分もできそう」というものを例示していきましょう
講師役を務めることのメリットを知ってもらいましょう
講師役を務めるメリットがイメージできた方が、引き受けてもらいやすくなります。考えつくことを洗い出し、講師就任要請の際に活用しましょう。
【こんなメリット】
- ・みんなから感謝される ※人に役立つことはモチベーションも高まります
- ・みんなから尊敬される
- ・自分の業務を知ってもらえ、協力してもらいやすくなります
- ・自分自身の勉強になる ※これが大きいです 下記参照ください
一番育つのは教える人 『教えること』は最強の自分教育
『教育』とは決して、教え育てるものではありません。教える立場の人自身が、教え育つものなのです。学ぶときは、自分の知識が足りなくても、問題は大きくありませんが、教えるときには、知識を体系立てて、しっかりと把握しておく必要があります。
人に教えるには、学ぶときの何倍ものパワーをかけて、自分自身でわかりやすく情報を整理して、ポイントをしぼっておかなければなりません。それだけの時間と工数をかけたことは、誰よりも自分自身が一番勉強になっているのです。人に教える機会というのはなかなかないものです。非常に貴重な経験になりますので、自ら積極的に参加するとともに、社内にも広く呼びかけましょう。
人事考課制度への反映
人材育成に貢献した人を評価するしくみを導入しましょう
例)講師回数を人事考課に反映させる
社内スカウト任命
講師就任を依頼する「口説き役」の適任がいれば、講師増が見込めます
例)「○○の資格持ってるんだって?すごいね!少し教えてやってよ」
例)「○○さんのワザを少しでもみんなが使えたら、状況は変わるんだけどな」
社内講師へのハードルを下げましょう
講師が「教えやすい方法」を増しましょう
紙上講師
講師は資料作成のみで、受講者は研修資料で自己学習
Web講師
パソコンを使った研修(イントラ、インターネット等利用)
音声講師
声(+音)だけで研修を実施
QA講師
質問形式でQ(質問)に対するA(回答)のみ対応
実践講師
ビデオ上で技術を披露(インタビュー形式でポイント解説)
※やりやすい方法をいくつもそろえておけば、講師を受けてくれる人も増えてきます