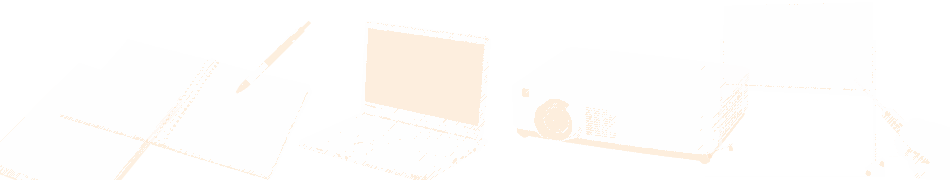『中途採用者育成プログラム』
等閑(なおざり)にされがちな『中途採用者研修』
中途採用の場合、突発的な事情によることが多く、中途採用者に対して計画的な研修を実施できていないケースが多くあります。欠員が出たからと、とりあえず人員補充を最優先し、入社後の研修をどうするかを十分に検証できていないのです。
「誰が研修をするのか?」
「どう研修するのか?」
「何を研修するのか?」
「どれだけ時間をかければいいのか?」
「研修ツールはあるのか?」
「どれくらいの能力とスキルがあるのか?」等々、
実施に至るまでの道は平たんではありません。何もない、何も決まっていない状況の中で研修をすることほど、効率の悪いことはありません。
このような事態を回避するために、ベースになるツールの準備と講師の配置を強くおすすめします。自社で仕事をする上で、必要不可欠な知識が学べるツールと、その内容を教えることができる人材がいれば、何の心配もいりません。まず、この整備からスタートすることが重要です。
新人研修のベースになるツール『社内ベーシック』
新たに入った会社で仕事をするには、まずその会社のことを知る必要があります。そのためのツールとして、『社内ベーシック』を準備しましょう。これに沿って学べば、会社の沿革から概要、事業領域、参入市場動向、経営理念、企業理念、方針等がわかるようになります。
毎年経営データ等を更新していき、最新版を準備します。この『社内ベーシック』は全従業員が毎年受講(閲覧)し、内容を理解するようにします。誰でも教えられるようにしておくことで、ベースの研修はいつでも実施可能になります。
現行の能力・スキルを確認しましょう
中途採用者を、どれだけ短期間で即戦力化できるかは、保有している能力やスキルによって変わります。採用にあたっては、ビジネスマナーからパソコンスキル、業界知識、業務知識、所有資格、経験職種、人的能力等を把握しておく必要があります。
不足部分があれば、どのように対処するかを具体的な実行計画としてスケジュール化します。ここをあいまいにしないことが、何よりも重要なことです。育成のための工数がかかり過ぎるようなら、採用を断念する選択も考えるべきです。
負担を少なく対応できるしくみを作りましょう
配属先でのOJTは必要ですが、できるだけ業務に直結したことだけを教えるようにします。そのためには、会社のルールをわかりやすくしておくことと、必要な情報にアクセスしやすい環境を整備しておく必要があります。具体的には、下記のような資料・ツール等を整備しましょう。
- ・「就業規則早わかり」
*就業規則をわかりやすく解説 - ・「社内申請手続き早わかり」
*社内で必要な各種手続きのやり方をわかりやすく解説 - ・『社内コミュニケーションポリシー』
- ・『社内言い回し辞典』、『社内用語辞典』、『業界用語辞典』、『ビジネス用語辞典』
- ・『調べ力』の習得