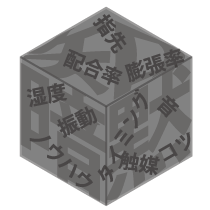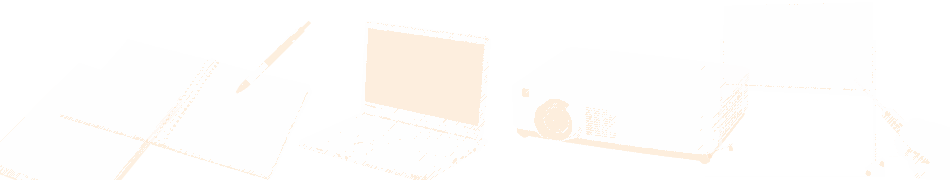暗黙知を共有化するコツ
暗黙知の中身は?
いい仕事をしたいと強く願いながら職務を遂行していると、毎日すこしずつ進化を続けるのでしょう。昨日よりも今日、今日よりも明日と、毎日の小さな積み重ねが品質の向上につながっていきます。長い年月をかけて試行錯誤を繰り返すことで、より質の高いものをつくり出すためのコツやノウハウを感覚的に会得していきます。
そのコツやノウハウというものは、現場での経験を通じて身につけてきたもので、第三者にその再現方法をカンタンに伝授できる性質のものではありません。このような属人的な知識のことを暗黙知(あんもくち)と読んでいます。
五官+αで察知?
視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、?覚

暗黙知を「わかる化」できない理由
暗黙知が誰にでもわかるようなカタチにできないのには、二つの理由が存在していると思います。一つは暗黙知を所有している人自身が、「どう説明すればいいか」がわからないという理由です。もう一つは暗黙知をわかるようにすることに対して、メリットを感じられていない可能性があるということです。
暗黙知を「わかる化」する方法
上述 2点の対策案
「説明しにくい」
・ヒアリング法 当事者から聞き出す
・質問法 知りたい人から質問形式で聞き出す
・観察法 みんなで見てノウハウを見つける
・対比法 名人個々のやり方を比較する
「メリットを感じにくい」
・暗黙知所有者を称える(自尊心)
呼称 名前を頂き、冠にする ○○法 ○○メソッド
マイスター、匠、師匠、名人、達人等々
暗黙知を誰にでもわかるようにするためには、手順を踏んで進める必要があります。”見えにくいモノ”を見えるようにするのですから、時間と工数がかかります。しかし、一度「わかる化」したモノは繰り返し活用できますし、鮮度も保ちやすくなります。ぜひ下記を参考に取り組んでください。
暗黙知を「わかる化」するための手順
- 1. 暗黙知の所有者をリストアップする
”知られている暗黙知 ”は当然のこと、”知られていない暗黙知 ”のリスト化も重要 - 2. 暗黙知共有化の重要性を宣言・明示する
(全社レベル)暗黙知を組織として共有する必要性を全従業員に理解してもらう - 3. 暗黙知所有者に協力要請を依頼し、了承を得る
当事者に納得の上、協力してもらうことが重要 - 4. チーム(2〜3人)を作り、複数人の目で観察する
数をこなす、いろんな角度から見る、気づいたことをメモする ビデオ撮影も検討 - 5. ヒアリング法で聞き出す(ヒアリング項目抽出)
観察で気づいた点などをヒアリングを通して検証し、暗黙知候補を抽出する - 6. 標準作業(基準書、マニュアル等に基づく)との“違い”に注目する
取り出した暗黙知候補と標準作業と照らし合わせて、相違点をあげる - 7. 暗黙知(コツやノウハウなど)を抽出する
相違点をさらに精査し、暗黙知だけを取り出す - 8. 暗黙知を反映させた標準作業書(マニュアル等)を作成する
暗黙知を取り入れ、再現できる内容のものに作り上げる - 9. 再現性を検証する
完成した標準作業書をもとに作業し、想定したモノが再現できるか確認 - 10. 精度向上を継続的にすすめる
完成した標準作業書も日々見直し、精度向上を図る