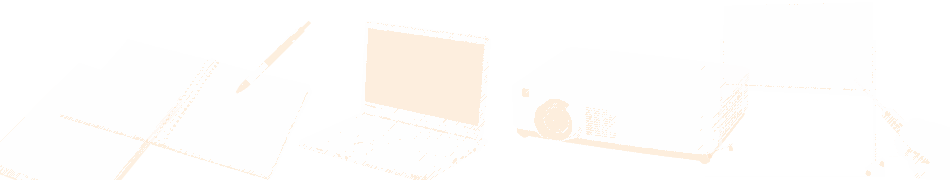「1対多」を知っておく
「1対多コミュニケーション」のプラスとマイナス
ITのおかげで組織の本部機構からの情報発信は、格段にやりやすくなりました。発信するメール文と必要に応じて添付資料を用意すれば、一度に大量送信することが可能です。アナログの世界のときは、人数分の書類を作り、送付先ごとに仕分けをして、発送するという作業が欠かせませんでした。

そういう時代から比べると、メールで完結できることは増えていますが、手軽に使えるがために、”副作用”が出ていることも否定できません。メールの数がやたらと増えたこともその一つでしょう。必要性の低い内容のものまで、”とりあえず”送られてくることはよくあります。しかし、もっと大きな問題は、内容を理解する必要性のあるメールが送られてくるときに起こります。
1本のメールがコスト拡大リスク?
たとえば、あなたが電子メールで、ある情報を発信したとします。送信する相手は社内の1,000人です。そのメールを開いて、内容を理解するのに3分の時間がかかるとしたら、1,000人だと3,000分の時間を使うことになります。仮に1人1分あたりのコストを30円(時給1800円÷60分)で計算すると、90,000円のコストがかかることになるのです。
書かれていることがわかりにくく、もし理解するまで5分かかったとすれば、60,000円(1,000人×2分×30円)余分なコストが発生してしまうことになるのです。「読解力を必要とする文章は、余計なコストがかかる」ことを知っておく必要があります。
発信する側はわかりやすく、短時間で処理できるメールを作成する必要がありますし、受信する側の人は、会社の状況や他部門のことをよく理解し、情報量が少なくても内容を把握できるように努力しなければなりません。
受信者からすれば、「1対1」
組織の中で情報を発信する部門を経験した人は、「1対多」のコミュニケーションをしていることは当然理解できます。しかし、受信する側しか経験していない人は、送られてくる情報が、自分一人に来ていると勘ちがいすることがあります。
メールの文面もよく読まずに、すぐに電話をかけていろいろと質問を投げかけたりするのです。発信者は、大勢の人にメールを送っているので、会社のあちらこちらから、問い合わせがくるのです。そういった事情を理解してもらうような啓もう活動をやっていくことも、ときには必要になります。
従業員同士のコミュニケーションマナーも啓もうしていきましょう