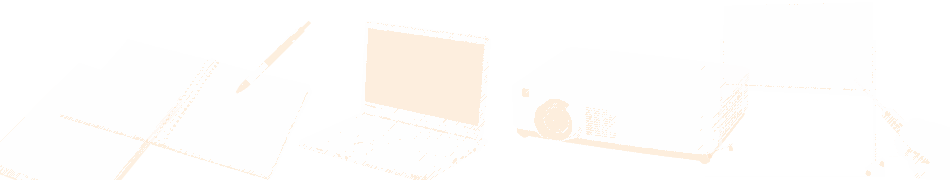問題作成も能力向上の機会
脳に汗をかく
研修実施後、受講者の習熟度を測定するには、確認テストを実施することが望ましいです。受講者、主催者双方が共通のモノサシで測ることができます。テキストの作成に加えて、テスト問題の作成も大変な作業です。しかし、問題作成を進める際、とても頭を使いますので、問題作成者自身の能力アップにおおいにつながっていきます。
答えを導き出すための「出題」をどう組み立てていくかで、受講内容の理解度の深さも決まっていきます。”脳にたくさん汗をかく ”ことで、出題者、受講者双方の能力を高めることが可能になります。
出題形式について
出題形式については○×式、択一式、多岐選択式、穴埋式、記述式、論文形式等があります。また、組み合わせによっては、そのバリエーションは広がりをみせます。研修内容や受講者のレベルに応じて、どの出題形式が適しているかは違ってきます。
○×式を採用すれば、受講者は回答しやすいのですが、勘で適当に選ばれてしまう可能性があります。そこで、ある程度受講者が考える必要性のある択一式の利用をおすすめします。
「四者択一」式であれば、4つの選択肢の中から、「正しいもの」か「間違ったもの」を選びます。当てずっぽうでは正解を導きだすことは困難ですので、習熟度の確認には適しています。
出題作成のポイント
問題数は多ければ多いほど、活用範囲が広がりますので、とにかくできるだけたくさんの問題を作ってみましょう。出題に適しないものは、削除するなり改良するなりが可能ですので、量を優先してください。作成のポイントは、出題文、解答ともできるだけ短くすることです。長い問題、解答は敬遠されてしまいます。
組み合わせを考える
作成した問題を広いテーブルなどに広げて、俯瞰(ふかん)しながら見てみると、出題の偏りに気づきやすくなります。いろんな機会に問題を利用できるよう、組み合わせを考慮しながら問題作成を進めましょう。
難易度調整ができればプロレベル
出題の難易度によって、受講者の得点は異なってきます。出題者側が平均点を予測し、うまく誘導する問題を作成できるようになれば、プロレベルです。このレベルをめざしましょう。