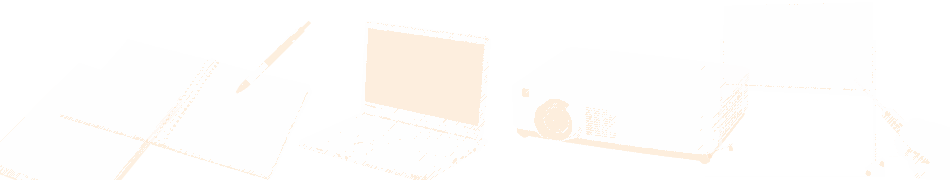『人材育成担任制』を取り入れる
人の成長というものは、短期間で見えてくるものではありません。ある一定期間、見守り続けることで、成長の軌跡が見えてきます。
受験最難関校として知られる関西の中高一貫校では、中学入学から高校卒業までの6年間、学年を受け持つ先生を変えないシステムを導入しています。生徒たちの進級に合わせて、先生も一緒に学年が上がっていくのです。
中学1年生から、ずっと生徒たちをみていると、各人の得手不得手もわかり、成績を伸ばすための対策もより的確に行えるのです。生徒にとっても、先生方が自分のことを良く理解してくれているという安心感もあるので、勉強に集中しやすくなっています。
企業も同じように、従業員の成長を見守り続ける人が必要になっています。人材を適材適所でいかしていくためには、中長期的な観点で個々人の特性をいかした戦略的な育成に取り組んでいくことが重要です。
担任の適任者
理想は社長が担任になるのが一番よいでしょう。少なくとも関与はしていくべきですが、状況によって難しい場合は、人事部門等に専任の人を配置することが望ましいです。当然、人員規模などにより、他業務との兼務になることもあるでしょうが、見守る側の環境が変わってくると、せっかくの成長の軌跡がぼやけてしまいます。しっかりとした体制で臨みましょう。
所属先上司との連携
担任は直接指導をする所属先の上司とは互いに連携を取り合いましょう。直属上司が身近すぎて気づかないことも、距離をとった立場の担任なら気づくこともあります。当然、逆のパターンもありますから、相互に情報を共有しながら、本人にとって一番望ましいカタチの育成方法で推進していきましょう。
成長、変化の兆しのつかみ方
社内活性化のヒントとして、「みんなの意識をいかす」で毎年1回、心に感じていることを文章で表現することを提案しています。感動したこと、気づいたこと、感謝したことについて400〜1200文字で表現してもらうという内容です。これは、1年間の仕事を通じて、意識がどう変化してきたかを見ていこうというものです。毎年継続的に続けていけば、時系列でつかむことが可能です。また、1回 /年以上、本人との面談を実施し、直接人間的な成長も確認しましょう。
担任の特別な役割
人は日々の業務の中で、ストレスやプレッシャーを感じることが少なくありません。特に新卒で入社した場合などは、慣れない環境の中で悩みを抱えがちになります。そんなときに、愚痴を聞いてくれたり、悩みを相談できる相手がいることは、非常に心強いものです。話を聞いてあげるだけでも、気持ちは楽になるものです。カウンセラーとしての活躍も期待されています。